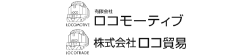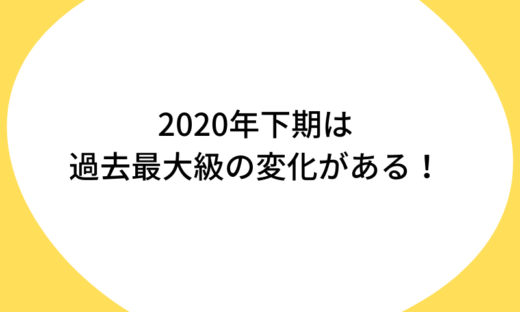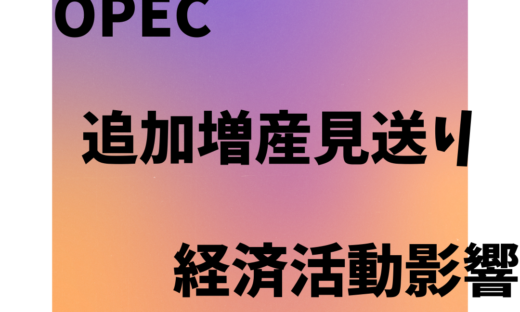プラスチック環境への大きな一手
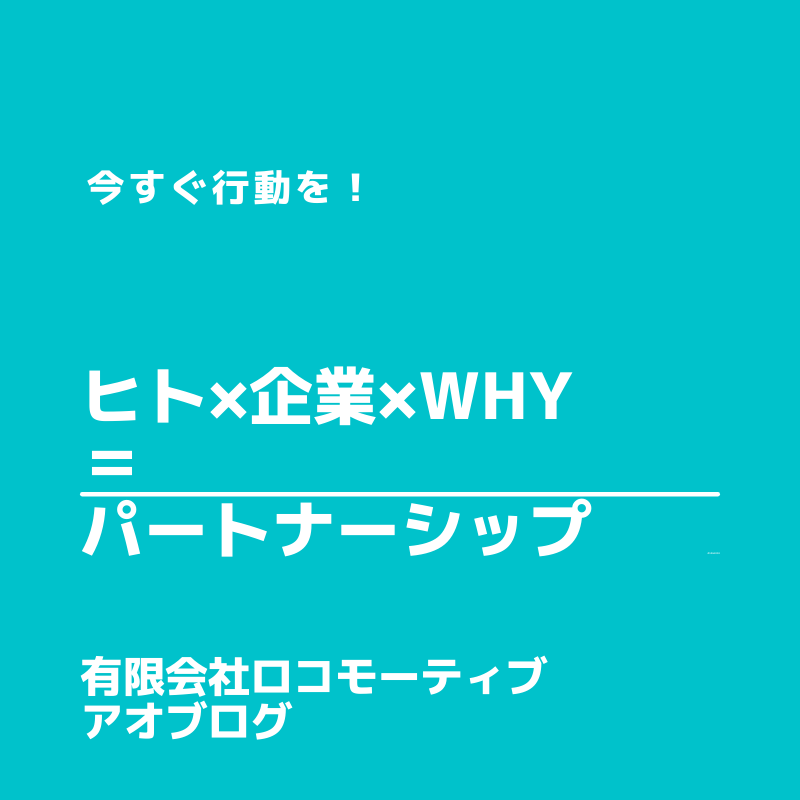
いらっしゃいませ!!
プラスチック問題に対する意識を皆様はどのくらい持っていらっしゃいますか?
先日のブログでも弊社は学生に対して、プラスチック問題について
お話しする機会をいただいている旨お伝えいたしました。
学生の考え方や環境、未来に対する想いが強く、
弊社としてもとても勉強となりました。
そこで、今回はSDGsの内容も踏まえて、
プラスチック問題に大きな一手を指した企業の動きをいくつかご紹介させていただきます。
皆様の会社でも参考になるかもしれないですし、事業のヒントにもなるかもしれません。
それでは、いってみましょう!
廃漁網をサングラス素材へ
まず一つ目は、廃漁網を使ってサングラスの素材としている例です。
リファインバース社とJINS社の協業となります。
宮城県石巻市の廃漁網を100%活用したサングラスで、
リファインバース社は海水中で使用された廃漁網やシリコンコーティングされた
エアバック生地を原料とした、リサイクルナイロン樹脂を製造販売しています。
そのリサイクル樹脂を原料として、
JINS社にてナイロンサングラスを生産している流れです。
ポイントとしては、海洋プラスチック問題の影響もある廃漁網を
価値あるものに生まれ変わらせるというコンセプトのもと、
リサイクル樹脂メーカーと生活品メーカーの協業した好事例です。
海水中の廃漁網やエアバックなどの原料は、他国でも非常に重宝されており、
争奪が激しい素材になるのですが、国内循環でかつ安定的なパートナーシップを
結んだうえでの本事例は、単純な価格競争等に巻き込まれない、
大きなメリットがある内容と言えるのではないでしょうか。
廃プラをケミカルリサイクル(パートナーシップ)
二つ目は、まだ検討段階の内容となりますが、
廃プラスチックをケミカルリサイクルで新素材製造に使用していくという内容です。
協業検討会社はBASFジャパン社と三井化学社となります。
日本国内におけるプラスチック廃棄物のリサイクル課題にケミカルリサイクルで
応えていく革新的な技術においてパートナーシップを結んでいく動きです。
ちなみに、BSSFジャパン社は別の案件でも、ケミカルリサイクルを通じて、
熱分解油に変換するという協業事例を持っています。
ケミカルリサイクルという技術的な革命を用いて、
新事業を拡大していく好事例と考えることができそうです。
100%リサイクルPETボトル
3つ目は皆さんご存じの方も多いかもしれません。
2018年に発表された、容器の2030年ビジョンとして、
コカ・コーラ社は100%リサイクルボトルにおけるボトルtoボトルを手がけている。
現時点の成果として、
今年の5月31日から主要商品に100%リサイクルPETボトルを導入。
1本あたり約60%、コカ・コーラ全体で年間3万5千トンのCO2排出量削減、
さらに、
新規で製造するPETボトルに対して3万トンのプラスチック削減を見込んでいます。
直近実績では、清涼飲料事業におけるPET樹脂使用率は28%(20年実績)だが、
主力商品への100%リサイクルPETボトル導入により、
22年にはコカ・コーラ社全体で50%のリサイクルPET樹脂使用率を計画中です。
PETボトル業界は以前にもブログ記事にした通り、大きな動きになっています。
その主力の一つとして稼働しているのがコカ・コーラ社ということですね!!
プラ再生の循環を見える化
最後にプラスチック再生の循環を可視化している事例をご紹介いたします。
「ブループラスチック」プロジェクトとして、活動をしている旭化成社です。
当該会社は資源循環社会の実現のために、
デジタルプラットフォーム構築を目指しています(日本IBM社の技術支援)
この技術は再生プラスチック製品におけるリサイクル素材の使用率の表示や
関与企業の可視化をすることで、消費者の行動変容の促進します。
エシカル消費と言えば、イメージが湧きますでしょうか?
商品タグ等にあるQRコードの読み取りによる
ブロックチェーントレース技術を使用し原料から製品までのトレースを行います。
消費者の意識改革、そして素材メーカー(リサイクル原料メーカー)から、
最終製品加工メーカーまでの一連のストーリーを消費者に可視化することによる、
パートナーシップ締結が特徴の大きな動きです。
プロトタイプがどうやら、2022年3月末までに実証実験をするとのことです。
いかがでしょうか。
これ以外にも、例えば市町村独自で活動していたり、
プラスチック業界以外にも、このような大きな動きが出ています。
そして、そのスピードはとても速いです・・・
全てを知ることは難しくても、何も知らないというのは決して好ましくないと思います。
業界内外問わず、いずれにせよ問題解決には共通する点が多くあるのではないでしょうか。
業界を超えたパートナーシップ協業も積極的に実践していくことも
今後の経営には必要になっていきますね!!
それでは、いってらっしゃい!